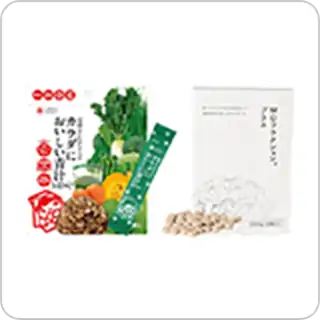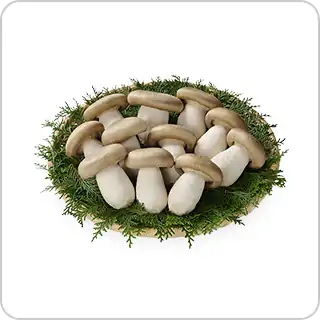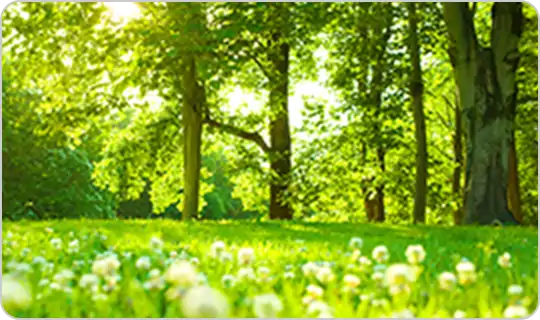きのこ大百科:
山できのこをみかけたら
マークの説明 :

美味しい

貴重

注意

危険
近くの山編
サクラシメジ

秋のクヌギ、コナラ、ブナなどの広葉樹林内に発生します。カサは5~12センチ、表面の中央はワイン色です。クキは3~8センチで、初めは白色で後にカサと同じ色になります。
少し苦味がありますが、歯切れが良くクセはありません。
採取後は、傷みが早いので注意が必要です。

タマゴタケ

夏から秋のシイ、ナラ、ブナ、モミなどの樹下に発生します。日本、中国、北アメリカなど広く分布しています。カサは6~18センチで周囲に溝線があります。クキは10~20センチで黄色に赤色の模様があり、上部に橙色のつばがあります。クセがなく舌触りがよく歯ごたえがよい。根元の白いつぼは味がないので取り除いて調理しましょう。

ナラタケ


春から秋の広葉樹や針葉樹の枯れ木に群生します。カサは4~5センチで表面は黄褐色です。クキは4~15センチで下がやや膨らみ、黄褐色から後に黒っぽくなることが多いです。全世界で分布が確認されていて、古くから食べられている有名なきのこです。歯切れ、舌触りがよく美味しいですが、食べ過ぎによる腹痛や生で食べると中毒を起こすので注意しましょう。

ハナイグチ


夏から秋のカラマツ林の地上に発生します。カサは4~10センチ、お饅頭形から平らに開きます。表面は赤茶色で粘りけがあります。クキは5~7センチで、つばから上は網目があります。ぬめりがあり、甘い香りが少しします。北海道や東北北部で好まれ食されています。幼菌はナメコをしのぐ風味が味わえます。食べ過ぎると消化不良を起こすので要注意です。

ハツタケ

夏から秋のアカマツ林やクロマツ林などに発生します。カサは5~10センチで、表面には環紋があります。クキの長さは2~5センチでカサとほぼ同じ色をしています。カサは傷つくと暗赤色の液を出し、やがて緑色のシミとなり残ります。古くから食用として知られていて、肉質はかたいですがもろく、口あたりはボソボソしてあまり良くありません。しかし、大変良い香りと旨味がでるので、お料理には幅広く利用されているようです。

コウタケ


秋にマツの混じった広葉樹林内に発生します。日本の特産種です。アサガオ形に開いたカサは10~20センチ、表面は淡茶色で次第に反り返った厚いささくれで覆われてきます。独特な香りとほろ苦い歯切れの良い風味の逸品です。ただし、生で食べると中毒を起こすので注意しましょう。

クリタケ

秋の広葉樹の枯幹や倒木、切り株に発生します。カサはレンガ色で3~8センチ、クキは長さが5~10センチ。苦味の成分のファシキュロールFを含んでいるため、わずかに苦味があります。

ヤマドリタケ

夏から秋の針葉樹林に発生します。色は美しい赤褐色。カサは大きく肉厚で管孔は初め白色ですが次第に緑がかります。風味にはクセが無く、カサは舌ざわりがよく、クキは歯切れがよいのでいろいろなお料理に合います。きわめて美味しいきのことして、ヨーロッパでは最高級の食用きのこの一つとされています。薄く切って乾燥させれば、さらに香りが増します。

森林編
マツタケ


秋のアカマツなどの松林に発生します。そのほか、コメツガ、ツガ、アカエゾマツ、トドマツなどの森林にも発生する日本の代表的な食用菌です。カサは8~20センチ。表面は褐色ではじめはお饅頭形、そして平らに開き、縁の部分が反り返ります。クキは長さが10~20センチで白色です。

アカハツ

夏から秋のアカマツ、クロマツなどの樹下に発生します。カサは5~10センチ、表面は淡い橙赤色です。クキは3~5センチでカサと同色です。細かくつぶして調理すると格別な味わいが楽しめます。

クロカワ


秋のマツやモミ林などの地上に発生します。カサは5~20センチ、表面は丸い山形で黒褐色です。クキは太く円柱状でカサと同じ色です。

シモコシ

10~11月ごろの砂地の松林に発生します。カサは5~10センチ、お饅頭形から中高の平らに開き、淡い黄色で中央は帯褐色です。クキは4~7センチで、太くて短いです。外見はキシメジとよく似ていますが、苦味がなく風味は優れています。歯切れの良さとしっかりとした食感が魅力です。

ニンギョウタケ

秋のマツやモミなどの針葉樹林に発生します。全体が20センチ以上になる集合型のきのこです。カサは肉厚で扇状です。表面は平らでクリーム色です。シャキシャキした歯切れが楽しめるきのこです。

ヒメカバイロタケ

夏から秋のコケに覆われた針葉樹の倒木や切り株に群生します。カサは0.8~2センチで表面は褐黄橙色です。クキは1~3センチで、下の方は褐色です。食用としては向いていません。

白樺・ヤチダモ編
カンバタケ
カバノキ属の枯れ木に発生します。カサは丸い山形で、表面は淡い灰褐色です。クキは横に太くなっています。

キヒダタケ


夏から秋の広葉樹(ブナ)林の下に発生します。カサは2~6センチ、表面は灰褐色でお饅頭形から開き、逆円錐形になります。
クキは3~7センチで黄褐色です。今まで食べられてきましたが、体質によっては軽い中毒を起こすことがあるので注意したいきのこです。

ドウシンタケ

夏から秋の針葉樹林や広葉樹林に発生します。本州から九州に分布しています。カサは4~12センチ、灰褐色で周囲に溝線があります。クキは上部に灰色のつばがあります。

ホシアンズタケ
北海道で見られ、腐った木、特にニレに発生します。カサは平らで、表面は肉色、網目のしわがあらわれることが多いです。

北海道・東北編
マイタケ


秋にミズナラやシイ類などの大木の地際に発生します。分岐したクキと扇形のカサをもつ肉質のきのこで、幅が30センチもの大きな株になります。自生するものを見つけるのは難しいですが、その香りは極めてよいです。

タモギタケ

初夏から秋のニレ、ヤダモチ、ナラ、カエデなどの倒木や切り株に発生します。カサは2~6センチで普通は円形で平らに開き中央部がへそ状にくぼんでいます。表面は淡黄色でひだは多少黄色をおびています。クキは白色・やや黄色。味はクセがなくサッパリした風味。ゆでると弾力が出て歯切れがよいです。

サクラシメジモドキ

秋の針葉樹林内に発生します。カサは6~12センチ。表面は粘りけがあり、ワイン褐色です。クキは3~10センチで繊維状でカサとほぼ同じ色です。

マスタケ

夏から秋のツガなどの針葉樹の幹に発生します。肉がマスの肉色に似ていることからマスタケと名付けられたと言われています。朱紅色で半円形のカサが重なり合い、全体で20~30センチにもなる大型のきのこです。若いときだけ食べることができ、柔らかさが魅力のきのこです。

近畿・四国・九州・沖縄編
ムラサキヤマドリタケ


夏から秋のコナラ、クヌギ、シイなどの広葉樹林や松などの混成林に発生します。カサは5~10センチ、表面は湿ると粘りがあり暗紫色です。クキは7~9センチで白い網目模様があります。希少価値は高く風味も良いです。

オオイチョウタケ

夏から秋の森林、竹林、公園などの地上に発生します。特に杉林内によく発生します。カサは7~25センチで表面はクリーム色です。クキは5~12センチで白色です。

オオツガタケ

夏から秋のツガなどの針葉樹林に発生します。カサは5~10センチ、表面はぬめりがあり、きつね色でお饅頭形から平らに開いてきますが、縁は内側に巻いています。クキは7~15センチ、白色で円柱形でで太く堅いです。舌触りや歯切れが良く、まろやかな風味です。

オオムラサキアンズタケ


夏から秋に針葉樹林内地上に発生します。大型で鮮やかな紫色をおびています。

サンゴハリタケ

秋の広葉樹の倒木に発生します。全体的に白くカサが無く珊瑚状に枝が伸びていき、10~20センチになります。見つけたときのうれしさが風味を一層増してくれます。

ムラサキシメジ


広葉樹林の地上に発生します。カサは6~10センチ、初めは美しい紫色で後に褐色になります。クキは4~8センチで根本が膨らんでいます。口当たりがよいが、生で食べると中毒を起こします。